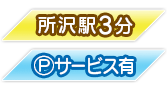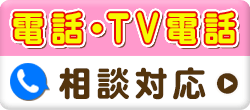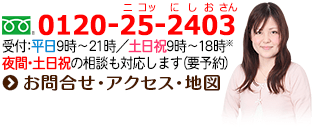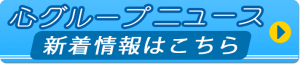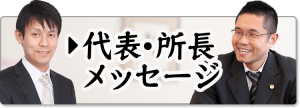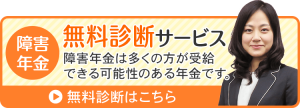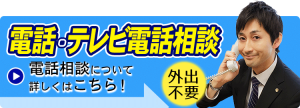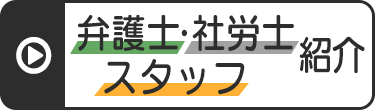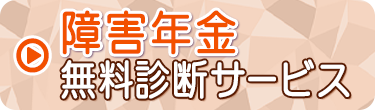障害年金を受給することのリスクはあるのか?
1 老齢年金が少なくなるリスク
障害年金の等級が2級以上の場合、届出を行えば国民年金保険料を納める必要がなくなります。
これを「法定免除」といいます。
老齢基礎年金の金額は保険料を納付した期間の長さに応じて計算され、法定免除が適用された期間は、保険料を納付しなくても当該期間に対応する2分の1の金額が老齢基礎年金に反映されます。
逆に言うと、反映される金額が2分の1ですので、保険料を全額納付した場合に比べると、老齢基礎年金の額は少なくなります。
もっとも、障害年金の等級が2級に該当したとしても保険料を納付するという選択ができるため、将来の老齢基礎年金を減らしたくなければ、保険料を納付すれば問題ありません。
また、いったん法定免除の適用を受けても、10年以内であれば追納が可能です。
ただし、平成26年3月以前に遡って2級以上に認定された場合、それ以前の期間については自動的に法定免除が適用され、納付済の保険料が返還される点には注意が必要です。
2 勤務先に知られるリスク
障害年金を受給することになっても、そのことを勤務先に伝える必要はありません。
そのため、通常は、自分から申告しない限りは勤務先に障害年金を受給していることを知られることはありません。
もっとも、障害年金を受給している傷病と同じ傷病で健康保険の傷病手当金を受給する場合、傷病手当金の支給申請書に障害年金の受給または請求の有無を記載する欄があるため、この支給申請書を勤務先に提出すると、障害年金を受給していることを勤務先に知られるリスクがあります。
3 扶養から外れるリスク
障害年金受給者の方が社会保険で家族の扶養に入っている場合、受給者の方の収入が障害年金を含めて年180万円以上になると、扶養から外れてしまいます。
4 寡婦年金、死亡一時金がもらえなくなるリスク
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての加入期間が10年以上ある夫が年金を受け取る前に亡くなってしまった場合に、妻に対して夫が受け取るはずだった年金額の一部を、妻が60歳から65歳になるまでの間に限り支払うという制度ですので、夫が障害基礎年金を受給していた場合は、遺された妻に寡婦年金は支給されません。
また、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を36か月以上納めた人が年金を受け取る前に亡くなってしまい遺族基礎年金も支給されない場合に、遺族に支払われるもので、亡くなった方が障害基礎年金を受給していた場合は支給されません。
5 他の年金や給付金と支給調整がなされるリスク
障害年金と同時に、生活保護、労災保険からの給付金、傷病手当金などの他の年金や給付金を貰っている場合は、他の年金や給付金の額が支給調整によって少なくなるリスクがあります。
もっとも、支給調整後の金額と障害年金との合計額が、障害年金を受給しない場合よりも低くなるということはありません。